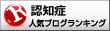前回は、発達障害の気質を強く持つ人ほど認知症になりやすいため「予防」が大事になるということと、認知症疾患は「発病」してから「ある一定以上」に脳細胞が減少して初めて「発症」するというお話をしました。
今回はその続きになります。
「脳を耕す」ことは認知症の「予防」にも繋がる
もともと脳を耕していた人と、あまり脳を耕していたなかった人では認知症のなりやすさに違いはあるのでしょうか。
それはもちろん「ある」と考えられます。
脳がしっかり深くまで耕されており、脳細胞が多くて脳神経ネットワークも発達しているような人では、多少脳細胞が脱落したとしても、まだまだ機能している脳細胞や脳神経ネットワークが十分残存していることから、すぐに認知症の症状が出現するようなことはないと考えられるからです。
つまり、たとえアルツハイマー型認知症などの認知症をもたらす神経変性疾患を「発病」していたとしても、実際に「発症」するまでには一定期間・タイムラグがあり、その期間がどのくらいの長さになるのかについては、その人がどれだけ脳を耕していたかに掛かっているということです。
さらにいえば、たとえ病気を「発病」していたとしても、その症状を一生「発症」させないということも決して不可能なことではないと考えています。
脳は耕せば耕すほど、認知症の「発症」に至らせないだけの脳機能の余力や貯金を増やすことができるのです。
ただ、そうはいっても人間の脳細胞というのは、病気の有無に関わらず、加齢によってどうしても減っていく傾向があります。
そのため何もしなければ、時間の経過とともにどんどん脳細胞は減っていってしまいます。
しかし、以前もお話したように「脳細胞はいくつになっても増える」ということが近年明らかになってきました。
そうであるならば「よく使う機能は発達し、あまり使わない機能は衰える」という「脳の可塑性(かそせい)」は、いくつになっても期待できるということです。
さらに、脳細胞を増やすには、運動、外出、勉強といった活動がとても有効であることも近年分かってきました。
神経変性疾患や加齢によって、確かに脳細胞は変性・脱落していきやすいけれども、日常的にこのような活動にしっかり取り組んでいけば、新たに脳細胞を増やしたり、脳神経ネットワークを発達させていくことも可能だということです。
まさしく「赤尾の豆単」の前書きに「人間は忘れる動物である。忘れてもよい。忘れる以上に覚えればよいのである」とあったように、認知症を「発症」させないためには、変性・脱落していく脳細胞の量以上に、脳を耕して脳細胞を増やしたり、脳神経ネットワークを発達させていけば良いのです。
そのことを身をもって証明されていたのが「きんさんぎんさん」だと言えます。
きんさんぎんさんは「きんは100歳。ぎんも100歳」というCMで一躍有名になりました。
きんさんぎんさんは100歳を超えていましたが、それでも心身ともに元気でしっかりしており、しかもそのお話はとてもユーモアに富んでいたのを覚えています。
その後、きんさんぎんさんはそれぞれ107歳と108歳で他界されていますが、実はぎんさんは長寿研究のために病理解剖されています。
そして病理解剖の結果、ぎんさんの脳には非常に強い萎縮が認められ、アルツハイマー型認知症の原因のひとつとされている老人斑(アミロイドβ)が多かったことから、脳だけみればまさしく「重度のアルツハイマー型認知症」の状態だったそうです。
しかし生前の様子からは、とてもそんなに重い認知症があるようには見えませんでした。
そうすると、やはり認知症疾患は「発病」していても「発症」させない方策があるのではないかと考えざるを得なくなります。
「脳を耕す」ことは認知症の「予防」だけでなく、認知症の「改善」にも役立つ
実は、きんさんはメディアに取り上げるまで「1から10まで数えることができない」ほどの認知症を患っていただけではなく、歩くこともできない状態だったそうです。
それがテレビに出演したり、頻繁に多くのメディアに取り上げられるようになってから、どんどんしっかりしてきたというのです。
おそらく多くの人たちが頻繁に訪れる存在となったことで、それまでよりも緊張感のある、メリハリある生活を送れるようになったことが非常に良かったのだと思われますが、実際きんさんぎんさんの生活習慣には「認知症」を改善させたり、「健康寿命」を伸ばすヒントがあると考えられ、2人の生活様式が専門機関で研究されてきました。
そして特に2人の食生活や運動習慣、新聞やテレビをよく見ていたこと、多くの人と交流する生活などが良かったのではないかと考えられるようになったのです。
まず、食生活については、動脈硬化や血栓を予防する効果のあるDHAやEPAを多く含む青魚を毎日のように食べていたこと、夕食はいつも世代の違った多くの家族と一緒に食卓を囲んでいたために、自然とバランスよく様々な食材を取り入れられていたことが良かったのではないかと考えられています。
実際に解剖を担当医師によると、脳の動脈や全身の大血管は年齢から考えると驚くほどしなやかで「動脈硬化」はごく軽度であり、「大げさではなく30歳か40歳若い状態だと思った」そうです。
運動習慣については、きんさんは一旦歩けなくなったものの下半身の中心とした筋力トレーニングに取り組んで徐々に歩けるようになったこと、さらにその後はきんさんもぎんさんも日課として30分以上散歩していたことが良かったのではないかと考えられています。
実際に、きんさんは「歩けなくなったら人間おしまいだ」と、ぎんさんは「人間は足からダメになる」とよく言っていたそうで、とにかくよく歩いていたというのです。
また、2人とも新聞をよく読んだり、テレビのニュースや国会中継をよく観たりしていて、世の中の動きにずっと関心を持ち続けていました。
いくつになっても新しいことを知る楽しさを求めて、好奇心を失わなかったことが、2人の生きる原動力になっていたのではないでしょうか。
そして多くの人と交流することで、とにかく「よくしゃべる」ことが特に良かったのではないかと考えられています。
ぎんさんは「わしらは双子だったから長生きできたんだね」と話していたそうですが、お互いが話し相手になってずっとおしゃべりしてこれたことが自分たちの長生きの秘訣だと考えていたようです。
さらに、たくさんいる家族とおしゃべりしていたことや、100歳を超えて人気者になってからはもっと多くの人たちとおしゃべりできるようになったことが良かったのだと考えられています。
日常的に色々な人と楽しく交流するだけでも「脳を耕す」ことができる
実際に人間にとっては、他の人たちと交流して社会性を保つということがとても大事なんだと思います。
他の人たちと言葉やジェスチャー、気持ちなどをやりとりしてコミュニケーションをとるというのは、とても高次なレベルの脳活動が必要とされるからです。
例えば誰かと会話する時には、相手の話や想いを受け止めて自分の気持ちや言いたいことを伝えなければなりません。
そのため、このような当たり前で何気ないやりとりをするだけでも、脳は大きく活性化されるのです。
このことを思い知らされたのが、今回のコロナ騒ぎです。
この間、コロナの感染対応のために、デイサービスをしばらくお休みしなければならない患者さんが続出しました。そうしたら、何人もの人がボーっとして反応が悪くなったり、会話もスムースにできなくなったりと、認知症の一気に進行してしまったのです。
さらに、その後しばらくしてデイサービスが再開し、また通い始めたら、少しずつですが顔や目の表情、受け答えの様子が以前の状態まで戻ってきたのです。
これにはとても驚きました。
しかしこのことを通じて、認知症のある人たちにとっては、デイサービスに通うことがいかに大切なことなのか、つまり定期的に外出して色々な人たちと交流することがいかに大切なことなのか、ということを改めて教えてもらったような気がします。
つまり、日常的に色々な人たちと交流したり、楽しくおしゃべりするだけでも、脳を大きく活性化させて「脳を耕す」ことができるということです。
きんさんぎんさんの例や、デイサービスを再開した患者さんの認知症の症状が改善していった例が、そのことを物語っていると言えます。
「脳を耕す」という視点で考えれば、高齢でも仕事を続けていたり、若い時から続けている趣味や得意なことがあって、いくつになってもそれに打ち込んでいけるというのは、確かに有利でしょう。
しかし、実際にそのような人というのはごく少数派であり、限られていると思います。
「脳を耕す」ためには、必ずしも専門的な難しいことを考えたり、行ったりしなければならないというわけではありません。
日常的にいろいろな人たちと楽しくおしゃべりするだけでも良いのです。
ただ毎日そのおしゃべりを継続していくことができるかどうかが大切になります。
そうすると、おしゃべりを楽しめる気心の知れた親しい人がいるのかどうか、そもそもおしゃべりするのが好きなのかどうかということも大切になるでしょう。
もちろん「おしゃべり」でなくても良いのです。
自分が楽しいと思えることを見つけ、それを毎日継続していくことこそが「脳を耕す」うえでは一番大切なことになると思うからです。
さいごに
ここまで25回にわたって「発達障害ともの忘れ」についてお話ししてきました。
このお話をするそもそもの出発点は「認知症外来を受診される患者さんの多くが、発達障害の気質を強く認める」ということでした。
そして「なぜそうなんだろう」ということから、色々なことを調べたり考えたりしてきたことをもとに、これまでお話ししてきました。
そして私がこのシリーズで一番お伝えしたかったことは、「発達障害の気質というのは、強弱の差こそあれ誰もが持ち合わせているものだ」ということであり、誰もが「認知症」になる可能性を少なからず有しているということです。
しかし、誰もが「できれば認知症にはなりたくない」と思っているはずです。
「ではどうしたらいいのか」ということで、「発達障害の気質が強いほど認知症になりやすい」のであれば、「認知症の予防や改善」について探っていくうえで「発達障害」を追求していくことが少なからず役に立つのではないかと考えたのです。
「自分が食べた物から自分の身体ができている」のであり、「自分が活動してきた結果が今の自分である」ということは間違いありません。
そうすると、その人がどのような生活を送ってきたかが、認知症の「発病」と「発症」にも密接に関与しているはずです。
ちなみに私は「身体と心は一体」であって、そうすると「自分の食べた物から心もできている」のではないかとも考えています。
実際、人間の心と身体の働きをコントロールしているのは、部位や領域は違えど同じ「脳」であり「脳神経」なのですから。
いずれにせよ「今まで自分がやってきたことの結果が今の自分である」のであれば、「よく使う機能は発達し、あまり使わない機能は衰える」という「脳の可塑性」が「認知症の予防や改善」においても、ひとつのキーワードになると考えました。
そして脳をたくさん使って「脳を耕す」ことが、認知症になりやすい傾向にある発達障害の人にとっても、認知症を予防・改善するうえで大いに役立つと考えたのです。
それは、たとえ認知症を「発病」している人であっても同じであり、場合によっては認知症を「発病」している人でも「発症」させないことや、「発症」している症状を改善させることも十分あり得ると考えています。
私たちは何度もそういった症例を経験してきているからですが、今回のシリーズでも「発達障害の気質」が強い方で、もの忘れを主訴に来院されてきた比較的若い3症例について、診断と治療経過を含めてご紹介いたしましたので、どうぞご参照ください。
今回のお話が少しでも皆さまのお役に立つのであれば、とても幸いです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
【お知らせ】
これまで週1回のペースで記事を更新してまいりましたが、諸事情により今後は不定期にしていくことにいたしました。
毎週楽しみにお読みいただいていた方には、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。
記事の掲載は不定期になりますが、今後とも「認知症診療あれこれ見聞録」をどうぞよろしくお願いします。
↑↑ 応援クリックお願いいたします