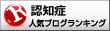まなざしによるケア(2)
前回は、まず認知症の人は相手の表情や態度に意外と敏感であるというお話をしました。
それは、失語症状が出て相手が何を言っているのか分からなかったり、自分の置かれている状況が分からないと、会話をしている相手や周りにいる人たちの表情などから、必死にその場の状況や雰囲気だけでも探ろうとするからではないかと思われます。
また、そもそも「相手の目を見ながら会話をする」ということは「あなたのことを見てますよ」というメッセージにもなり、相手に安心感を与えることができるということですが、逆に「相手が目を見てくれない」ということは、その人に対する不信感・不安感のもとになり、本人に少なからずストレスを与えることにもなり得るとお話ししました。
今回はその続きになります。
「目を見ない」応対は認知症を進行させかねない
「認知症の人の目を見ないことなど、大したことないのでは」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし前回お話ししたように、認知症の人は、言葉の理解力や記憶力の低下を補うために、接している相手や周りにいる人たちが「何を考えているのか」「どんな気持ちでいるのか」について、さらには場の雰囲気や流れを何とか把握しようとして、その人たちの表情の変化にとても敏感になります。
認知症の人は「顔の表情」という視覚情報に頼らざるを得ないということです。
そしてこの「顔の表情」というのは「目の表情」に依るところが大きいのではないでしょうか。
そのため、認知症の人は自分の世話をしてくれる人が目を見てくれなかったりすると、いくら口で優しく丁寧に話しかけてもらったとしても、大きな不安感を抱きかねません。
認知症の人にとって、相手が「自分の目を見てくれないこと」は大きなストレスになるのです。
それにも関わらず、こちらの認識が不足していたり、忙しかったりすると、いつも認知症の人の目をしっかり見ながら応対する、ということができなかったりします。
そもそも認知症の人はストレスに弱い傾向があり、ちょっとしたストレスでも認知症の病状を悪化させたり、進行させてしまいかねません。
そのため、認知症の人に対するケアの大原則は、できるだけ本人に「穏やかに過ごしてもらう」ということになるのですが、「目を見ない」応対は、それだけで認知症の人の心を大きく波立たせてしまい、ケアの原則にも反することにもなってしまいます。
ここで、人がコミュニケーションをとる時に「見た目」がどれほど大きく影響するのか、ということを示す「メラビアンの法則」というものがありますので、それをご紹介します。
1971年にカリフォルニア大学のアルバート・メラビアンという心理学者が「感情や気持ちを伝えるコミュニケーションをする時に、どのような情報に基づいて相手の印象は決定されるのか」ということを検証しました。
そのために実施した実験で「『楽しいね』と言いながら、声のトーンは低く、不機嫌な顔をしている」というように、言葉と口調、表情・態度が矛盾している状況を何通りか作り、相手はどのような印象を抱くのかについて調べていったのです。
するとコミュニケーションにおいては、相手の印象を決定するのに「見た目」が55%、「口調」が38%、「会話の内容」が7%の割合で用いられる、ということが分かりました。
つまり、言葉でどんなに「楽しい」と言っていても、表情・態度や口調がつまらなそうであれば、「つまらなそう」という「見た目」や「口調」の印象の方が非常に強く伝わる、ということになります。
人と人とのコミュニケーションにおいては、言葉そのものの意味や会話の内容よりも、声の質や大きさ、話すテンポといった「口調」、さらには話すしぐさや表情、視線といった「見た目」の方が大きく伝わるということです。
特に「メラビアンの法則」によれば、「見た目」が相手の印象を決定する割合は55%であり、これは全体の半分以上にもなります。
「口調」を併せれば、何と全体の90%以上にもなります。
認知症の人に限らず、一般の人でも会話をしている時には、話の内容よりも口調や視線・表情によって相手の印象のほとんどが決まってしまうということです。
これは、言葉の理解力や記憶力が低下している認知症の人だったら、なおさらではないでしょうか。
したがって、認知症の人の応対をする時には「口調」や「見た目」に特に配慮する必要があるのです。
さらにいえば、「見た目」を大きく左右するのが「顔の表情」であり、その中でも特に「目の表情」が大切になると思います。
そのため、認知症の人と接する時には、こちらの表情や気持ちをしっかり伝えるためにも「相手の目を見る」ということが不可欠になるのです。
次回に続きます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
↑↑ 応援クリックお願いいたします