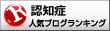本当に「耳が遠い」だけですか?(5)
前回は、当院で実施している「失語症スクリーニングテスト」と失語症が疑われるよくある回答や反応についてご紹介しました。
また、認知症患者さんの多くが言葉の視覚的理解よりも聴覚的理解の方が障害されやすい傾向があることについてもお話ししました。
今回はその続きになります。
「失語」の具体的な症状について
「失語」があると具体的にどのような症状が出現してくるのかについて、ここで一旦整理してみたいと思います。
「失語」とは、言葉を「聞く」「話す」「読む」「書く」ことが障害される症状になります。
もちろん脳の障害される部位やその大きさによって、障害される機能や程度は変わりますが、いくつかの機能が重複して障害されることも多いようです。
以下に、それぞれの機能が障害された時の特徴的な症状についてまとめてみます。
①言葉を「聞く」
・聴力は正常だが、聞いた言葉の意味が分からない
・特に大勢で話している時に会話の理解が悪くなった
・「難聴」に間違われやすい
・分かる言葉と分からない言葉があるため、いわゆる「都合耳」になった
・そもそも本人が理解できずに伝わっていないことでも、周りの人には「忘れてしまった」と勘違いされやすく「もの忘れ」と表現される場合がある
・話の内容が分からないために、急に怒ったり、笑ってごまかしたり、話を逸らしたりすることがある
・電話で一方的に自分の用件だけを話して切ってしまったり、電話で用件が伝わりにくくなった
・テレビを観なくなった
②言葉を「話す」
・言いたい言葉が出てこない、浮かばない(=喚語困難)
・言いたい言葉とは別の言葉を言ってしまう(=錯語)
・直前に自分が言った言葉や相手に言われた言葉を、文脈に関係なく繰り返して言ってしまう(=保続)
・短い文章や単語での表出が増え、長い文章で話すことが難しくなった
・口や舌の麻痺(=構音障害)がないのに、話がたどたどしくなった
③言葉を「読む」
・文字や文章の意味を読み取り、理解することができない
・漢字は読めるが、ひらがなやカタカナが読みにくい
・新聞や本を読まなくなった
④言葉を「書く」
・書きたい文字が思い出せない
・長い文章が書けずに、メモや単語レベルになった
・書き間違いが増えてきた
・漢字や文字を見て書き写すのが難しくなった
・日記などを書かなくなった
以上になりますが、もし上記したような症状を持つ人が周りにいらっしゃるのであれば、是非前回ご紹介した「失語症スクリーニングテスト」を実施してみてください。
それでもし「失語」症状が少しでも疑われるようであれば、できるだけ早く認知症専門医を受診することをお勧めします。
「失語」症状は「意味性認知症」でなくても出現しやすい
認知症疾患の中で一番多い「アルツハイマー型認知症」でも、経過とともに「失語」症状が表れてくることがあります。
ただ「アルツハイマー型認知症」の場合は、「記憶障害」つまり「もの忘れ」が発症早期から前景化することがほとんどであり、「失語」症状が出現してくるのは病状がある程度進行した中期以降になります。
「アルツハイマー型認知症」は記憶中枢である側頭葉内側の海馬の病変が先行し、病気の進行とともに病変が側頭葉前方部へ拡がってくることで初めて「失語」症状が出現してくるからです。
つまり「アルツハイマー型認知症」でない他の認知症を伴う神経変性疾患においても、病気が進行して脳の病変が言語中枢のある側頭葉に及んでくれば、当然「失語」症状を呈するようになるということです。
そのため、病気の進行に伴って「失語」症状を合併してくる認知症患者さんというは、決して珍しくはないのです。
ただ、明らかな「記憶障害」を伴わずに病初期から「失語」症状が前景化している場合には、やはり「意味性認知症」が強く疑われます。
その場合には、「意味性認知症」では「失語」の他にも病初期から出現しやすい特徴的な症状があるため、それらの症状の有無を簡単なテストで確認していくことになります。
次回に続きます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
↑↑ 応援クリックお願いいたします